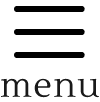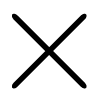Information
- 2026-01(1)
- 2025-12(2)
- 2025-11(3)
- 2025-10(3)
- 2025-09(1)
- 2025-07(4)
- 2025-06(2)
- 2025-05(2)
- 2025-03(4)
- 2025-02(1)
- 2025-01(3)
- 2024-11(4)
- 2024-09(2)
- 2024-06(5)
- 2024-05(4)
- 2024-04(1)
- 2024-03(3)
- 2024-02(2)
- 2024-01(2)
- 2023-12(2)
- 2023-11(2)
- 2023-10(1)
- 2023-09(4)
- 2023-07(1)
- 2023-06(2)
- 2023-05(2)
秋田の山とつながる、 八柳の樺細工展

.
実家や旅館、親戚の家なんかで見たことがある、という人は多いのではないでしょうか。
山桜の樹皮を使った、秋田は角館の伝統工芸・樺細工。
武士の副業としてはじまり、200年以上前から今日までその技が受け継がれています。
山に自生する山桜の皮をはぎ、乾燥させ、表面を削ることで艶のある風合いを出す。
そしてそれを、茶筒や箱などの外側に貼ることでさまざまな樺細工の製品ができあがります。
樺細工って、最初に書いた「実家や旅館、親戚の家なんかで見たことがある」もので、正直ちょっと渋いかなって思っていました。渋いというか、艶がすごくあって、ちょっとピカピカし過ぎなんじゃないかって。それが、どうも日常生活の中で居場所を見つけられないように感じていました。
だけど、実はそれだけじゃない。
もっと樹皮感を残したものや、木の模様を活かしたものなど、今は特に「樺細工はこうじゃなきゃいけない」みたいなものが時代と共にアップデートされ、その素材と技をそれぞれに味わえるたくさんのバリエーションがあるのですよね。
樹皮そのものの個性を、どんなふうに選び、活かしているのか。
使っていくとどんなふうに変化していくのか。
そんな話を聞くたびに、もっと樺細工のことを知りたくなってきました。
そしてさらに気になること。
木の皮は、どこでどうやって採っているのか。
それは持続可能なのか。
山の課題は?
などなど。
丸ごと含めた、秋田の山とつながるような展示にしたいと思います。
今回展示をしてくださる八柳さんは、伝統的な樺細工を、どうやって今の暮らしの中にフィットする形で使ってもらうのか。まず知ってもらうことを大切に、クラフトフェアなどにも出店。シンプルでより素材の良さを感じられるものづくりを進められています。
と同時に、古いもののお直しにも対応。その修理についてInstagramなどでも発信されています。
投稿でみた、代々受け継がれてきた樺細工の薬籠。
剥がれた皮が美しく貼りなおされた様子は本当にかっこよかった。
こうして長く使っていくことこそが樺細工の本来の良さであり、そういうものを手に入れたい。と思ったのでした。
樺細工に馴染みのある方も、まだイマイチその良さが分からない、という方も、是非この展示をきっかけにより良く知ってみませんか。
定番の茶筒(コーヒーにも)、シンプルな箱、それからブローチなどの小物、いろいろなものを届けてくださいます。
それぞれに複数個の在庫をご用意くださる予定なので、皮の表情を見比べてお選びいただける大変貴重な機会です。
また、初日の21日(金)と22日(土)はワークショップにトークも企画しています。
別途ご案内いたしますので、どうぞお楽しみに。
【秋田の山とつながる、八柳の樺細工展】
2025年11月21日(金)-26日(水)
12:00-18:30 *最終日は16:00まで
〇11月21日(金)18:00~ /22日(土)11:00~
ワークショップ「樺細工のコースター/ブローチづくり」(1.5hくらい)
〇11月21日(金)19:30~
トーク「秋田の山とつながる、八柳の樺細工」
詳細、お申込みは追ってお知らせいたします。
トークはざっくばらんに、秋田のお酒とともに!という目論見ですよ!
*お茶もあります