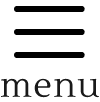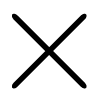Information
- 2026-01(1)
- 2025-12(2)
- 2025-11(3)
- 2025-10(3)
- 2025-09(1)
- 2025-07(4)
- 2025-06(2)
- 2025-05(2)
- 2025-03(4)
- 2025-02(1)
- 2025-01(3)
- 2024-11(4)
- 2024-09(2)
- 2024-06(5)
- 2024-05(4)
- 2024-04(1)
- 2024-03(3)
- 2024-02(2)
- 2024-01(2)
- 2023-12(2)
- 2023-11(2)
- 2023-10(1)
- 2023-09(4)
- 2023-07(1)
- 2023-06(2)
- 2023-05(2)
羊毛に触れるワークショップ 【フリースマットづくり】

羊毛そのままの色を生かしたものづくりをされる、ホームスパン作家、beigeのササキトモミさんによる「羊毛に触れるワークショップ -フリースマットづくり-」を開催いたします。
これまで、1日教えてもらって残りは家で完成させる、というスタイルでやってきましたが、今回は【2日間で仕上げる】コースをプラス。
1回5時間×2日間の、トータル10時間。長い道のりですが、ギュッと集中して完成させる達成感は心地よいものになりそうです。
もちろん、1日だけ教えてもらって残りは自分で、というのもあり。どちらかお好みでお選びください。
さて、そのフリースマット。
写真のような羊の原毛を使ったモフモフとした座布団、のようなもの。椅子の上にのせてもよし、そのまま座布団として使ってもよし。しっかりと厚みがあるのでキャンプやピクニック、お花見などのアウトドアでも頼りになりますよ。
綿の経糸に羊毛を少しずつ括り付けていくような方法で制作します。テンションを保ちつつ、根気強く。
みんなでおしゃべりしながら、羊毛の風合いに癒されましょう。ウールヒーリング、という言葉もあるくらい、羊の毛に触れていると気持ちがゆったりとあたたかくなります。
『羊毛に触れるワークショップ フリースマットづくり』
●日時
1日目/2月6日(金) 11:30~16:30
2日目/2月7日(土) 11:30~16:30
※どちらの回も途中で休憩を挟みます
●参加費
①2日で完成させるコース(2/6金+2/7土)
37,400円(材料費・お茶代込み)
※木枠はレンタルです。お持ちの方はご持参いただいても◎
②1日だけ(2/6金)
23,100円(材料費・木枠代・お茶代含む)
③1日だけ(2/7土)
23,100円(材料費・木枠代・お茶代含む)
1日だけのコースは途中まで制作、最後に仕上げの方法を教えてもらい、ご自身のペースでご自宅で仕上げます。
●持ち物 はさみ(通常の工作用でOK)・エプロン・大きめの袋(30cm×40cmの織り木枠が入るくらいのもの・持ち帰り用)
●場所 土脈 新宿区神楽坂6-16 2F
お申込みはこちらより
以前参加して仕上げが出てきていない、や、もう一度確認したい、という方はその旨ご相談ください。
TERASの刺し子展2026 - 刺し子から見る多様な世界 -

2026年最初の展示は、昨年一昨年と回を重ねるごとに好評な
「TERASの刺し子展」- 刺し子から見る多様な世界 - の第三弾。
(※English is below)
栃木県の就労継続支援事業所「TERAS」で生まれる刺し子小物からウェアまで、一堂にご覧頂く展示です。
TERASは、生きづらさのある方々の継続的な就労支援を通し、その居場所や社会との接点、仕事を生み出していくことを目指し活動するブランドであり団体。求められるものづくりをすること、持続性があること。それぞれの個性が認められるものであること。それらを刺し子を用いたものづくりを通して模索、表現、挑戦しています。
はじめて目に留まったのは、素敵な刺し子作品でした。
誰が、どこで作っているものなんだろう。興味深く話を聞いてみて初めて就労継続支援事業所が手掛けるものと知ったのでした。とはいえ、その事業所って?
そこで手を動かす人のこと、仕組み、法律。接点がなければほとんど知らないことばかりですが、こうして刺し子作品との出会いを通して関心の分野が広がり、理解を深められることには大きな意味があるように感じます。
社会にはいろいろな人がいて、いろいろな場所がある。
まずはそんなことを、刺し子から見て、知って、考えるきっかけにしていただけると嬉しいです。
※写真は2025年の様子
今回は足を運びやすいよう会期を週末2回を含む前半・後半に分けて、人気のワークショップも土曜日と水曜日に開催。
会期前半・23日(金)には、TERASのスタッフ、山中さんをお迎えし前回も好評だったトークイベントを開催いたします。
就労継続支援事業所って?という初歩的なところから、持続可能な活動にしていくための苦労や、原宿の商業施設「ハラカド」でのお話、TERASのこれからの活動の広がりなども伺えたらと思っています。
トークイベントの詳細、ご予約はこちらよりどうぞ
ワークショップは以前に参加された方も楽しめるよう、新たに【刺し子の布のはぎれを使ったポーチづくり】として企画。テンプレートを使って簡単な刺繍にも挑戦できるようパワーアップしました。
一枚の布状のものを仕上げてもらい、後日ポーチの形に縫製しみなさんのお手元へ。少しお時間を頂戴しますが、布が立体になって戻ってくる感動を楽しみにお待ちいただけたらと思います。
ワークショップの詳細、ご予約はこちらよりどうぞ
是非ご予定くださいませ。
TERASの刺し子展2026 -刺し子から見る多様な世界-
【日時】
前半:2026年1月21日(水)-24日(土)
後半:2026年1月28日(水)-31日(土)
12:00〜18:30
〇トークイベント
1月23日(金) 18:30〜
〇ワークショップ ※2hほど
1月24日(土) 14:00~
1月28日(水) 13:00~
参加費:6600円(税込)
【場所】 土脈
新宿区神楽坂6-16 2F
主催:jokogumo × 株式会社TOMOS company
TERAS supports independence through craftsmanship created at a continuous employment support facility in Tochigi Prefecture. It is a brand and organization dedicated to creating a sense of belonging, social connections, and work opportunities for individuals facing challenges in daily life through sustained employment support. They seek to create products that meet demand, are sustainable, and recognize each person's individuality. Through the craftsmanship of “Sashiko”, they continue to explore, express, and challenge themselves.
What first caught my eye was a beautiful Sashiko piece. I wondered who made it and where. Upon hearing the story with interest, I learned it was created by a continuous employment support facility. Until then, without prior connection, I knew almost nothing about such facilities—the people working there, the systems, the laws, etc.
Encountering this Sashiko piece broadened my horizons and deepened my understanding, which feels profoundly meaningful. Society is made up of diverse people and diverse places. I'd be delighted if Sashiko could serve as a starting point for seeing, learning about, and thinking about these things.
Knit&Homespun

2025年最後の展示となります。
Knit&Homespun
2025年12月17日(水)-22日(月)
12:00-18:00
その名のとおり、あたたかなニットとホームスパンのご紹介です。
糸選び、色選びが素晴らしいyourwearのストールやニットキャップ、
北海道からは丁寧に編まれたa.mo knitのミトン
また、手紡ぎ手織りのホームスパンは、お馴染みみちのくあかね会とササキトモミさんより届きます。
寒さもいよいよ本格的に。
首や手を引っ込め、ついつい縮こまってしまいがちですが、
お気に入りのニットやホームスパンがあると寒い冬もなんのその。
寒さも楽しみに変えて楽しく過ごしたいものです。
また、会期中のスぺシャル企画
みちのくあかね会オーダー会【わたしのヘリンボーン】
を、12月20日(土)・21日(日)の2日間限りで開催します。
グレー系・ベージュ系・ダーク系、3色の経糸を選んだら、今度は緯糸をたくさんの色の中から指定。
あなたのヘリンボーンマフラーをお作りいたします。(お渡しは来シーズンの予定です)
八柳の樺細工展 ワークショップ&トーク

【秋田の山とつながる、八柳の樺細工展】では、樺細工の展示販売だけでなく、樺細工のこと、またその素材のこと、山のことなども知っていただく機会にしたいと考えています。
まずは、樺細工がどうやってできているのかを知るためのワークショップ
樺細工のコースター/ブローチづくり
乾燥させた山桜の皮の表面を削り、膠をつかって木板に貼り付けコースターやブローチにします。
コースターかブローチ、どちらかをお選びいただけます。
【日時】
①11月21日(金)18:00~
②11月22日(土)11:00~
ワークショップ(1.5hくらい)各6名
【参加費】5,500円(税込)
◎お持ちいただくものは特にありませんが、木の粉や膠など、汚れが気になる方はエプロンや腕貫き等ご持参ください。
お申込みはこちらのフォームよりどうぞ
トーク「秋田の山とつながる、八柳の樺細工」
角館より八柳慶子さんをお招きし、八柳のものづくりや山との関わりについて、写真や資料、樺細工の道具や古いものなどもお持ちいただき、いろいろなお話を伺う機会といたします。山桜の皮を使った「樺茶」もしくは秋田のお酒、1ドリンクが付きます。飲みものを片手に、双方向でざっくばらんに質問なども交えつつ樺細工について学び、秋田の山に思いを馳せましょう。
【日時】
11月21日(金)19:30~(1時間程度)
【参加費】1,500円(税込)*1ドリンク付き
お申込みはこちらのフォームよりどうぞ
秋田の山とつながる、 八柳の樺細工展

.
実家や旅館、親戚の家なんかで見たことがある、という人は多いのではないでしょうか。
山桜の樹皮を使った、秋田は角館の伝統工芸・樺細工。
武士の副業としてはじまり、200年以上前から今日までその技が受け継がれています。
山に自生する山桜の皮をはぎ、乾燥させ、表面を削ることで艶のある風合いを出す。
そしてそれを、茶筒や箱などの外側に貼ることでさまざまな樺細工の製品ができあがります。
樺細工って、最初に書いた「実家や旅館、親戚の家なんかで見たことがある」もので、正直ちょっと渋いかなって思っていました。渋いというか、艶がすごくあって、ちょっとピカピカし過ぎなんじゃないかって。それが、どうも日常生活の中で居場所を見つけられないように感じていました。
だけど、実はそれだけじゃない。
もっと樹皮感を残したものや、木の模様を活かしたものなど、今は特に「樺細工はこうじゃなきゃいけない」みたいなものが時代と共にアップデートされ、その素材と技をそれぞれに味わえるたくさんのバリエーションがあるのですよね。
樹皮そのものの個性を、どんなふうに選び、活かしているのか。
使っていくとどんなふうに変化していくのか。
そんな話を聞くたびに、もっと樺細工のことを知りたくなってきました。
そしてさらに気になること。
木の皮は、どこでどうやって採っているのか。
それは持続可能なのか。
山の課題は?
などなど。
丸ごと含めた、秋田の山とつながるような展示にしたいと思います。
今回展示をしてくださる八柳さんは、伝統的な樺細工を、どうやって今の暮らしの中にフィットする形で使ってもらうのか。まず知ってもらうことを大切に、クラフトフェアなどにも出店。シンプルでより素材の良さを感じられるものづくりを進められています。
と同時に、古いもののお直しにも対応。その修理についてInstagramなどでも発信されています。
投稿でみた、代々受け継がれてきた樺細工の薬籠。
剥がれた皮が美しく貼りなおされた様子は本当にかっこよかった。
こうして長く使っていくことこそが樺細工の本来の良さであり、そういうものを手に入れたい。と思ったのでした。
樺細工に馴染みのある方も、まだイマイチその良さが分からない、という方も、是非この展示をきっかけにより良く知ってみませんか。
定番の茶筒(コーヒーにも)、シンプルな箱、それからブローチなどの小物、いろいろなものを届けてくださいます。
それぞれに複数個の在庫をご用意くださる予定なので、皮の表情を見比べてお選びいただける大変貴重な機会です。
また、初日の21日(金)と22日(土)はワークショップにトークも企画しています。
別途ご案内いたしますので、どうぞお楽しみに。
【秋田の山とつながる、八柳の樺細工展】
2025年11月21日(金)-26日(水)
12:00-18:30 *最終日は16:00まで
〇11月21日(金)18:00~ /22日(土)11:00~
ワークショップ「樺細工のコースター/ブローチづくり」(1.5hくらい)
〇11月21日(金)19:30~
トーク「秋田の山とつながる、八柳の樺細工」
詳細、お申込みは追ってお知らせいたします。
トークはざっくばらんに、秋田のお酒とともに!という目論見ですよ!
*お茶もあります